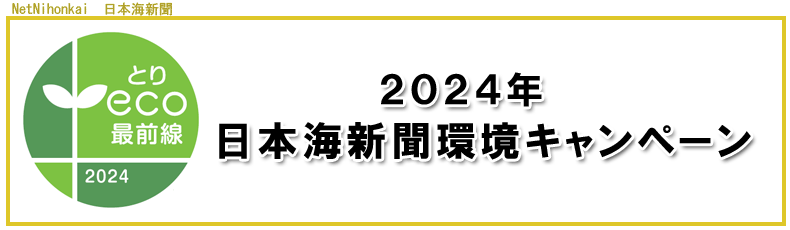相互に影響を与え合う環境と農業の関係性は深い。化学肥料や農薬の使用を抑えるなど環境への負荷を減らし、自然と共生する持続可能な農業の定着が求められており、鳥取県内でもこうした環境保全型農業が推進されている。中には環境だけでなく、人の健康にもメリットを見いだせる付加価値の高い農産物の生産を目指す動きもある。
若桜農林振興(若桜町若桜) 安心・安全なコメ生産に力 自然豊かな地で作る特別栽培米とエゴマ
 |
| 精米され、袋詰めされる特別栽培米 |
環境問題や食の安全性に関心が高まる中、鳥取県認証特別栽培米の「コシヒカリ」と無農薬で育てた「エゴマ」を栽培。安全な農産物の供給とともに土壌環境や生態系に配慮された、地球に優しい農法で地域活性へとつなげる。
若桜町は地域の95%が山林で自然豊かな土地、そこで育まれる水、標高の温度差という、稲作にとっての好条件がそろっており、2020年から農薬と化学肥料の使用量を最小限にとどめる「特別栽培」を実施。厳正な管理の下、乾燥から精米まで一括可能な町立施設で、安心・安全なコメの生産に力を入れている。
若桜農林振興を代表するもう一つの作物がエゴマ。6年前から同町固有品種の栽培を開始した。加工生産する「エゴマ油」は、着色料などを使わず無添加で、県内外のリピーターも多い自慢の一品だ。
今後は地元で生産される堆肥を使った、資源の地産地消と持続可能な栽培体制の構築を目指す考え。小林正樹社長(63)は「耕作放棄地を少しでも増やさないよう、自然を守りながら消費者に喜ばれる商品を提供していきたい」と話す。
いいだファーム(北栄町大島) 手作業こだわりビタミンC豊富 特別栽培農作物ブラックベリー
 |
| 特別栽培で収穫したブラックベリーを手にする飯田鈴子さん |
小さな粒が親指大の房になって実るブラックベリー。木イチゴの仲間で、肥大すると赤から黒色に色づく実と甘酸っぱく爽やかな味わいが特徴の果実だ。
ビタミンCやポリフェノールが豊富で抗酸化作用が高いことから「地域の人を元気にしたい」との思いで13年前、夫の飯田正征さん(76)が栽培に着手。農薬を使わず、肥料は鶏ふんのみの特別栽培農産物として鳥取県の認証を受け、妻の鈴子さん(77)らとともに10アールの黒ぼく畑で200本を栽培している。
土を選ばず作りやすいという利点はあるものの、無農薬ということで害虫駆除や除草などは全て手作業。繁殖力が強く枝の伸びも早いため、支柱に絡ませるなど誘引作業も随時必要だ。「大変だけど、栄養価に見合った安心安全なものを作りたい」と鈴子さん。実が完熟する7月の収穫時には近くの障害者施設の利用者らを招き、一つ一つ丁寧に手摘み作業を行う。収穫した実は鮮度を保つため瞬間冷凍し、ジャムやジュースへと加工。水や添加物を加えず砂糖のみで調整したこだわり商品は果実本来の味が楽しめると人気だ。鈴子さんは「環境に優しく、健康を担う産業として続けていきたい」と力を込める。
未来へつなぐ私のチャレンジ 公立鳥取環境大学通信
環境学部環境学科3年 福島 紀穂
新たな食文化「昆虫食」 試食体験通し可能性探る
 |
| 本年度開催した昆虫食イベントの様子 |
昆虫食は日本の文化の一部であることをご存じだろうか。“ゲテモノ”というイメージが根強く残る中、江戸時代以降多くの地域で日常的に食べられてきた歴史がある。タンパク質が豊富で、長野県ではイナゴのつくだ煮やザザ虫が伝統的に食べられてきた。
近年、地球温暖化や人口増加などの諸問題に加え、新型コロナウイルス感染症の影響で飢餓人口が増加している。少量で必要な栄養素を得ることができる昆虫食は、新たな食料としての可能性が評価されている。
私は、大学1年生の頃から毎年昆虫食のイベントを開催し、啓発活動を行ってきた。学生向けイベントでは、SDGs(持続可能な開発目標)と関連づけ、世界の諸問題を昆虫食から考える機会を提供。昆虫食の試食を通して匂いや食感、味を直接体験してもらい、昆虫食の偏見を和らげることを目指してきた。
現在、日本国内では昆虫食が嗜好(しこう)品として扱われることが多い。私は、健康食品として昆虫食を推したり、安全な食品として昆虫食を広めたりしたいわけではない。ゲテモノとして扱われ、日々偏見で語られる昆虫食が、未来の食文化の一部としての新たな可能性を秘めていることを一人でも多くの人に知ってもらいたい。(おわり)
わが社の環境(エコ)活動
株式会社白兎環境開発
鳥取市千代水4丁目/奥田貴光社長
海岸清掃通じ児童を応援
 |
| 例年児童らが参加して取り組んでいる海岸清掃の様子 |
産業廃棄物と一般廃棄物の処理、リサイクルを中心に手がける。海岸清掃を通じ、子どもたちに環境問題への意識を高めてもらう活動にも力を入れる。
毎年6月、スポーツに取り組む児童を応援し、環境保全意識を高めるイベント「HAKUTO DAY〜少年少女スポーツ応援企画」を実施。今年は天候不良で実施できなかったが、例年鳥取市内の小学校の野球チームに所属する児童と保護者らが海岸に集まり、ペットボトルや漂着した木々などを拾い集めるほか、同社社員が分別方法も解説している。
また、元プロ野球選手らによる野球教室と交流試合も同日に開催。スポーツを通じ、地域の未来を担う子どもたちを応援する事業として定着している。
大山日ノ丸証券株式会社
鳥取市吉方温泉/加生弘憲社長
環境問題やSDGs積極的に
 |
| 子ども食堂の代表に食品などを手渡す加生社長(右) |
地域密着で株式や投資信託、外国債券などグローバルな商品を取り扱う。さまざまな環境問題やSDGsへの活動を積極的に行い、地域貢献にもつなげている。
山陰海岸ジオパークを支援する中で、2008年に鳥取砂丘未来会議と「鳥取砂丘アダプトプログラム」の協定を締結した。年に1度、同砂丘の一画1ヘクタールの「里親」として、社員が除草活動を行い、景観保全に貢献している。
18年からは、読み終えた本を寄付して、貧困の状況にある子どもを支援する「こどものみらい古本募金」に参加。また、今年から株主優待で得た食品や生活必需品を子ども食堂に寄贈する活動も始めた。資源を必要な人に循環する取り組みも進める。加生社長は「次世代のためにも各活動を続けていきたい」と先を見据える。