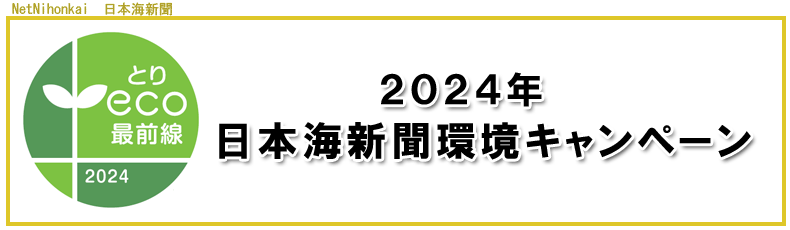「SDGs」「環境保全」「地球温暖化対策」などのワードは、持続可能な未来を築くための理念として、私たちの生活に溶け込んでいる。この理念実現手段の一つに挙げられるのが、再生可能エネルギー(再エネ)を利用して電力を生成する「創エネルギー(創エネ)」。企業や家庭で取り組むエネルギーの地産地消と自給自足が、「2050年ゼロカーボン実現」の推進力となる。
複合施設に自家消費型の太陽光発電システム導入 創エネでCO2排出量削減 日ノ丸産業
 |
| コンビニ、コインランドリーの屋上に設置された太陽光発電システム。ガソリンスタンドを含めた複合施設の自家消費を開始 |
創エネを代表する自家消費型の太陽光発電システムは、電力会社への売電方式とは異なり、同発電で作った電力を自ら消費するため、電気料金の負担軽減や二酸化炭素(CO2)排出量削減にも貢献できる。同時に余剰エネルギーは蓄電池などに貯蔵できるのも大きなメリットだ。
2030年までの温室効果ガス削減目標60%(国の目標値は46%)に掲げる鳥取県は、県内発電事業者や地域電力会社と取り組む初期投資ゼロの太陽光導入モデル「鳥取スタイルPPA」や市町村と連携した助成制度を進め、県内の創エネを後押しする。一方、鳥取県内企業・事業所のCO2排出量は、県内CO2排出量の全体の約4割を占めており、数値目標達成には民間事業者の取り組みも不可欠となる。
このうち、「まちにやさしく、ひとにやさしく」のキャッチフレーズの下、生活を支える多彩な事業を展開する鳥取市の「日ノ丸産業」は、地域のエネルギーインフラとして石油やガスの安定供給から、太陽光発電や蓄電の創エネ需要にも応えている。
昨年12月には、ガソリンスタンドとコンビニ、コインランドリーを併設した山陰初の複合施設「ENEOS Enejet鳥取駅南SS」(同市富安2丁目)に太陽光発電システムを導入。同社の13カ所目の発電施設で自家消費型施設となった。複合施設のコンビニとコインランドリー屋上に高耐圧ソーラーパネル96枚(出力36キロワット)を敷き詰め、発電した電力は3施設の電気を賄う。
同施設の昨年2月からの1年間で総電力使用量は約20万キロワット時。同システムが本格起動する本年度、この外部電源分22%削減と、年間の約20トンのCO2削減を見込む。天候の条件次第では、同施設の日中使用全電源を太陽光のみでカバーすることが可能で、環境に配慮した事業を進めている。
また、同社では家庭向けの太陽光発電システムの導入サポートにも注力。県内外で3月末現在540軒(蓄電池を含む)の一般家庭などで運用されており、小山尚悟常務は「一般家庭も太陽光発電を設置すれば、年間でCO2約1・5トンの削減になるといわれている。太陽光やLPガスなどの地球に優しいエネルギーを生かし、各家庭や企業で実践できる新しいライフスタイルを提案していきたい」と話している。
遊び通しSDGs伝える TORICEF(鳥取県ユニセフ協会学生部)
 |
| SDGsを楽しく学ぶをモットーに企画、運営する |
遊びや工作を通じて、地域の小学生が持続可能な開発目標(SDGs)を学べる場を提供。今の社会課題を理解し、解決に向けて自ら考える身近な機会となっている。
鳥取大生33人が所属する鳥取大公認サークル。もともとカードゲームや絵本を使ったイベントを開催しており、昨年度から「さらに小学生がSDGs目標に親しめることを始めたい」と新たにSDGs工作教室を始めた。
SDGs工作教室は、鳥取市役所や企業の協力を得て、牛乳パックやトイレットペーパーの芯などの廃材を収集。それらを材料に貯金箱や万華鏡などに加工することで“再利用”の意義を伝え、子どもたちの環境意識を育んでいる。
鳥取市協働推進課と連携して準備を進め、昨年10月から同市内の公民館など13カ所で実施し、好評を得た。本年度も同教室を展開する予定だ。
今後は新たに同市内の小学校での出前授業を目指す。鳥取大地域学部3年の倉内言実前代表は「子どもたちと関わっていると、SDGsの名前やアイコンは知っていても、世界の実情までは知らない子が多い。小学校の授業にSDGsの内容が加わることで、持続可能な地域づくりにつながっていけば」と話す。
わが社の環境(エコ)活動
中国電力株式会社鳥取支社
鳥取市新品治町 森田秀樹支社長
若者が環境と地域考えるきっかけに
 |
| 生徒と積極的にコミュニケーションを図る河崎担当 |
持続可能な未来を切り開く上で重要なエネルギーに関わる企業として、SDGsの普及啓発や実践促進を行う鳥取県の「とっとりSDGs伝道師」制度に基づき、次世代を担う若者が環境問題や地域社会を考える機会をつくる。
エネルギー情勢に関心を持ってもらった上で地元への愛着を育てるきっかけになればと、県内の小学校や公民館などで出前授業を開催してきた。今年1月には河崎忠義広報グループ担当が同伝道師に任命され、初の講演会とワークショップを3月21日、米子高で実施。同校1年生約140人に向け、持続可能なまちづくりや脱炭素社会の実現を解説した。
河崎担当は「地域と共に発展していくため、今後も啓発活動に加え多様な活動に取り組んでいく」と力強く語る。
株式会社ホームズ
倉吉市八屋 牧井健一社長
高機能な省エネ健康住宅
 |
| 快適さと省エネを両立した、明るく開放的なリビング |
持続可能な開発目標(SDGs)を企業理念の柱に据え、家づくりを通じて「健康」と「豊かな未来」の実現を模索する。「住む人が心から温まる家づくり」をモットーに、NE―ST(ネスト)やZEH(ゼッチ)仕様の高機能な省エネ健康住宅を提案している。
鳥取県産材を新築全棟に採用し、地産地消の推進に取り組む。また、心地良い住環境を保つため、温度や湿度を絶妙なバランスでコントロールする独自の仕組みを持ち、寒暖差のある季節でも一定の快適な空気を循環。最小限の冷暖房機器で省エネ化と家全体の温度差をなくす「温熱的バリアフリー」をかなえた。
健康、省エネにこだわり、家族構成や住む人のライフスタイルに合った最適な家づくりをアドバイスする。
株式会社エナテクス
倉吉市清谷町2丁目 福井利明社長
循環生み出す地域づくり
 |
| ソーラーシェアリングでドクダミを栽培する施設 |
「地産地消の再生可能エネルギー」の普及を目指しCO2削減の取り組みを多岐にわたって展開。鳥取県の豊かな自然から創出できるエネルギーを利活用し、地域の社会と経済と自然が一体となって、循環を生み出す持続可能な地域づくりにつながっている。
同社を含めた民間企業のほか、倉吉市・北栄町・琴浦町が出資する地域新電力会社「株式会社鳥取みらい電力」が供給する電気は、全てCO2排出係数ゼロ。民間事業者や一般家庭にも供給先を広げることで、地域のゼロカーボン化を後押ししている。
また、ソーラーパネルの下を活用し太陽の光を、農作物の生育と発電とで分かち合うソーラーシェアリングを実施。遊休農地を有効利用し、原木しいたけの栽培やドクダミの栽培を行いながら、自然と地域の共生を目指している。