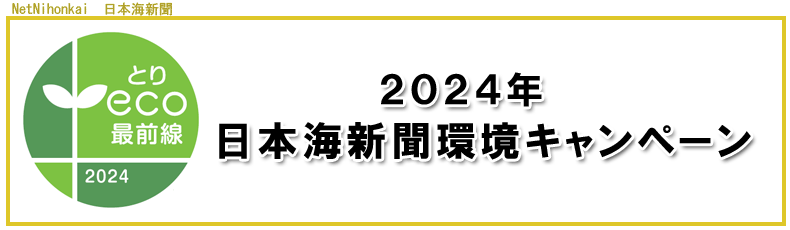| 特集一覧 |
2025 











2024 











2023 











2022 











2021 








2020 








2019 








2018 








|
|
|
vol.187 うみぽす甲子園
2025.1.29
好きなテーマを設定し海の課題解決に挑む高校生が、ポスター製作と具体的な活動、プレゼンテーションなどで競う2023、24年度の「うみぽす甲子園」(海洋連盟主催)で、鳥取県の高校から応募したチームが2年続けて決勝プレゼンに進み、特別賞を受賞した。取り組みの内容やその後の継承活動を紹介する。
辻田寛明 ソーシャルアクション賞
青谷高校青谷ごみ当番(5人)/青谷高
【テーマ】海をきれいに大切に
 |
| ソーシャルアクション同好会のメンバーとボランティア参加した青谷高の生徒たち |
鳥取の海の豊かさを未来につなげたいと、海洋ごみ問題と向き合った。地元の美しい海を守る取り組みを継承していくため、受賞チームのメンバーが中心となって24年春結成した「ソーシャルアクション同好会」(13人)が同年秋、海岸清掃と地引き網漂着ごみの多さを痛感したチームのメンバーたち。各地の海岸を回ってごみの状況を調べ、清掃して帰る活動のほか、観光客にも参加を呼びかけ、鳥取砂丘でごみ拾いイベント(23年10月)を実施したことなども決勝プレゼン大会で披露した。ポスターは鳥取砂丘をモチーフにデザインした。をセットにしたイベントを展開した。
◇漂着ごみの多さ痛感
23年当時、高校1年だった生徒有志(現2年)が、授業で行った海岸清掃の振り返りとして、コンテストに応募した。青谷高から3〜5人1組で応募した8チームのうち、決勝プレゼン大会に進んだのが「青谷高校青谷ごみ当番」だった。
 |
| ごみ拾いの後、地引き網に興じる子どもたち |
◇楽しみながら清掃
受賞から約1年後の24年10月、船磯海岸(鳥取市気高町)で行った同好会主催の「とっとり環境地引き網」は、「レッツエンジョイ!」をキャッチフレーズに地域を巻き込んだイベントとなった。地元の保育園児、小学生とその保護者約140人をはじめ、県漁協の関係者や鳥取短期大の学生ら地元のボランティアを含めて総勢約230人が参加した。
参加者全員で138袋分ものごみを拾った後、きれいになった海岸で地引き網に興じ、会場には子どもたちの歓声が響き渡った。
「メインはごみ拾いだが、何か楽しいことをセットにして、大勢の人を集めたかった」と話すのは、同好会の部長を務める山本柚花さん(2年)。「海洋ごみが生態系に与える悪影響、景観を損ねることなどを大勢の人に知ってもらい、海の課題解決に向けて地域のみんなで考えるきっかけになったと思う」と振り返った。来年度も子どもたちの笑顔を誘発できるようなイベントを検討中だ。
同好会の顧問教諭は「地引き網など楽しいこととセットにするのが“鳥取式海岸清掃”といわれるようになれば面白い。観光客にも入ってもらえばさらに盛り上がるし、鳥取の海岸清掃の新たな文化になれば」と同好会の活動に期待する。
石原良純 はじめま賞
Splash(スプラッシュ) whale(ホエール) Tori−nishi(トリニシ)<5人>/鳥取西高
【テーマ】 クジラが教えてくれること
 |
| 決勝大会会場でクジラの骨と記念撮影する受賞チームのメンバーら |
クジラの骨との出合いから、海洋ごみ問題に関心を持った自然科学部生物班の5人が、海の現状と問題への意識を浸透させるため活動を始めた。海ごみの半分以上を占めるプラスチックに焦点を当てたイベント出店や出前授業で、理解を次の人へつなげていく。
◇クジラの骨が漂着
2024年4月、湯梨浜町の海岸にクジラの死骸が流れ着いた。死骸の骨は生徒の学びに活用するため、一時的に鳥取西高に貸し出された。この骨を計測し標本にしようと、教師が同部の部員に声かけ。集まった5人のメンバーが計測を進め、クジラの死の原因を知る中で、海ごみ問題の根深さを実感した。
プラスチックには、有害物質を吸着する特徴がある。海に流出したプラスチックごみ(プラごみ)が微細なマイクロプラスチックとなって生物の体内に取り込まれ、付着していた有害物質が蓄積し死に至る。
「プラごみの悪影響の原因まで皆に伝えたい」と考えたメンバーは、クジラの骨から得た学びを広く知らせるために動き出した。
 |
| クジラの骨の重さを測定する大森さん(右)と児童 |
◇伝える連鎖の契機に
未来の海ごみを減らそうと、伝える対象は小中学生に設定した。手始めに24年9月、鳥取城跡でのイベントで、クジラの骨を触ったり、プラごみを使ってストラップを作ったりする体験ブースを設けた。約60人いた体験者の約半数が答えたアンケートで、全員が「環境問題に対する意識が深まった」と回答。問題意識を広めることができたことに手応えを感じた。
同12月には、久松小6年生44人が同チームの授業を受けた。城跡イベントで展開した2ブースに加え、海洋ごみを分別できる体験ブースを設け、海の現状への理解を深めた。「今日知ったことを周りの人にも話したい」と話す児童もいた。
「今後も小中学生に伝える活動を続けたい」と語るメンバー。しかし、クジラの骨はいずれ鳥取県立博物館に返却予定のため、新しい伝え方を見いださないといけない。リーダーの大森一芭さん(1年)は「海ごみ問題への意識を2人目につなげようという思いから伝播(でんぱ)していった。問題を自分ごとに捉え、周囲に伝えてもらうきっかけをつくり続けたい」と前を向く。
うみぽす甲子園とは
海の課題に立ち向かう高校生コンテスト。課題解決方法のアイデアをポスターにして、具体的な活動に展開、その成果を含めてプレゼンテーションする。予選通過したファイナリストが決勝プレゼン大会に臨み、グランプリと準グランプリ各1チーム、特別賞5チームを決める。2023年は全国29校・212チーム(ファイナリスト14チーム55人)、24年は全国39校・295チーム(ファイナリスト11チーム34人/敗者復活戦からの参加・再エントリー含む)の応募があった。日本財団「海と日本PROJECT」の一環で海洋連盟が22年から実施。
|
|