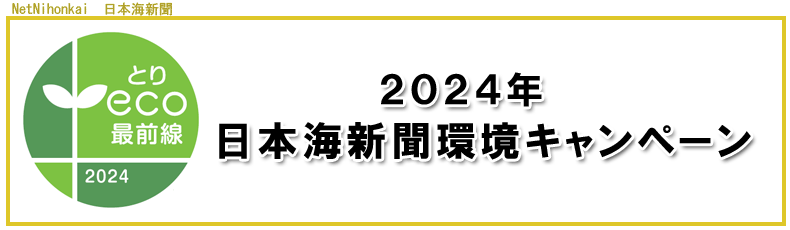| 特集一覧 |
2025 











2024 











2023 











2022 











2021 








2020 








2019 








2018 








|
|
|
vol.194車社会と地球の未来
2025.08.30
車は私たちの生活を便利にする一方で、環境に大きな負荷をかけている。国土交通省の発表によると、2023年度の日本の二酸化炭素(CO2)排出量(約9億8900万トン)のうち、自動車分野が16.5%を占める。国が宣言した50年のカーボンニュートラル実現に向け、車の電動化などの取り組みは重要性を増している。
電動化が開く新しい道
 |
| イベント時のEV協力隊登録車による給電の様子 |
◆普及進まず
移動手段を自家用車に頼らざるを得ない「車社会」の鳥取県。自動車検査登録情報協会によると、2024年3月時点で一世帯あたりの保有台数は1・435台で全国14位と高く、全国平均1・016台を上回る。
県内の運輸部門(自動車、トラック、バス、航空など)のCO2排出量は23年度時点で107万6千トン(暫定値)。県が掲げる30年度の目標値は89万4千トン(13年度比22・4%減)だが、基準とされている13年度比の削減率はわずか6・7%にとどまる。
達成率を上げるためには、排出量が多い自動車分野の見直しは欠かせない。中でも、エコカーの普及は有効な手立てだ。しかし、保有車両全体のうち、EVなど(PHVを含む)の普及率は0・51%(23年度末)と1%にも満たない。県は30年度までに普及率5%を目指すとしているが、道のりは険しい。
◆減税補助金
EVの普及を阻む要因の一つが、高額な車両価格だ。一般的にEVはガソリン車よりも導入費用が高いが、国は車両購入に対する補助金やエコカー減税を実施している。加えて、1キロ走行するための電気代がガソリン代より安いため、維持費を抑えられる利点もある。太陽光発電設備がある家では、自家発電した電気で充電できるため、さらに経済的だ。
一方、外出先の充電設備への不安も課題だ。県内のEV充電スタンドは、181拠点(住宅設置分を除く)。充電には時間を要するため、不安解消にはより多くの充電設備の設置が求められる。国は充電器普及のための補助金を交付し、経路充電(道の駅、SAなど)、目的地充電(商業施設、宿泊施設など)、基礎充電(集合住宅、事務所)の設置を進めている。
◆EV協力隊制度
鳥取県脱炭素社会推進課は、EVなどの普及に向け「とっとりEV協力隊制度」を実施している。県内のEV保有者が災害やイベント時の給電活動に協力をする制度で、18年に開始。23年度末時点で77台が登録されており、EVなどを緊急時やアウトドアの場面における電源としての活用法を広く知ってもらう狙いがある。
同課の担当者は「環境負荷低減のための選択肢の一つとして、EVなどのさらなる普及を目指していきたい」と語る。暮らしの足である車の今後の進化、充電インフラや支援制度の整備に注目し、一人一人が持続可能な社会の実現に向けた選択をしていくことが必要だ。
わが社の環境(エコ)活動
日産プリンス鳥取販売株式会社
(鳥取市千代水4丁目櫻井誠己社長)
EVの可能性伝える
 |
| レースを終え先導広報車のEVと記念撮影する選手たち |
電気自動車(EV)の多様な可能性を伝えようと、地域のイベントなどに積極的に協力する。鳥取県西部の代表的なスポーツイベント「全日本トライアスロン皆生大会」もその一つだ。
同大会のコースは距離が長く、高低差も激しい。EV発売当初の十数年前は協力がかなわなかったが、その後の進化で大幅に性能が向上。3年前からバイク、ラン競技で排気ガスの出ない先導広報車として活躍し、ゴール付近での電気供給も行っている。
今年の大会には2台のEVを投入。移動手段としてだけでなく、イベント運営や防災などEVの多様な用途の実践・実証を通じ、ノウハウを蓄積している。中津尾直己専務は「今後も車両性能の進化とともにEVの新たな可能性を追求していく」と力を込める。
有限会社中本産業
(湯梨浜町南谷中本紀昭社長)
放置竹林の伐採竹活用
 |
| 光合成活動が低下した放置竹林 |
山林破壊につながる放置竹林が拡大する中、竹やぶの光合成活動の低下を防ぐため、伐採した竹を消臭材やキノコ菌床材、竹プラスチック材として有効活用する研究を進めている。
光合成活動が低下した竹やぶは炭素吸収源としての機能や土地の保全機能の低下、生態系バランスの崩れなどを招き、さまざまな問題を引き起こしかねない。このため、環境問題に注視する中本社長が、竹やぶの光合成を進める際に伐採された竹をビジネスの視点で活用する方策を探っていた。
中本社長は「事業化が実現すれば、竹林の光合成が活性して、よりよい環境が生まれると思う。今後2年間は研究に励み、成果を見いだしていきたい」と力を込めた。
有限会社大成商事
(米子市夜見町 佐田山一成社長)
便利な「古紙ランド」
 |
| タイセイくんの古紙ランド花園店(米子市) |
家庭や事業所から出る新聞や雑誌、段ボールなどの古紙類を回収する「タイセイくんの古紙ランド」を運営する。
地域住民の利便性確保を第一に、無人化運営で24時間年中無休、いつでも利用できる体制を整えた。持ち込んだ古紙類の重さに応じてポイントが付与(午前7時〜午後8時)され、500ポイントためると500円のクオカードと交換。楽しみながら環境活動に参加できる。
2016年の境港店を皮切りに鳥取県西部で6店、島根県で3店を運営。ポイント対象外だが、西福原、境港、東出雲の3店では古着の持ち込みも受け付ける。今後は年内に淀江店がオープン予定。佐田山社長は「世界一きれいな資源回収施設を目指したい」と意気込む。
#私たちのグリーンムーブメント―若き担い手たち
 |
| ヤギとのふれあいを楽しむ家族連れ |
環境に優しい除草 公立鳥取環境大「ヤギ部」
環境保全と地域交流を目的に、活動を続けている。部員は約120人。大学構内の放牧地でヤギ4頭を飼育し、草原の維持や地域貢献に取り組んでいる。飼育は年中無休で、日々の世話や健康管理を学生が交代で担う。
放牧地ではヤギが草を食べることで森林化を防ぎ、絶滅危惧種を含む生物の生息環境を守っている。草原は全国的に減少傾向にあり、持続的な管理の意義は大きい。
また、地元の祭りや子ども食堂などにも“出張”し、ふれあいを通じて生物多様性や命の大切さを伝える。軽トラックで移動用小屋を運び、安全にヤギを連れていく。子どもたちの笑顔に「やっていて良かった」と実感する部員も多い。
一方で課題もある。飼料代や獣医費用は年間数万円に上り、冬季は裏山から木を切り出して与えることもある。夏場は熱中症、梅雨や冬はぬかるみや積雪が作業を妨げる。ダニ対策の薬品も高額で、資金面での支援が求められている。
部長を務める栗原隆行さん(環境学部2年)は「ヤギとの関わりを通じて、自然の変化や命の重みを感じるようになった」と話す。
|
|