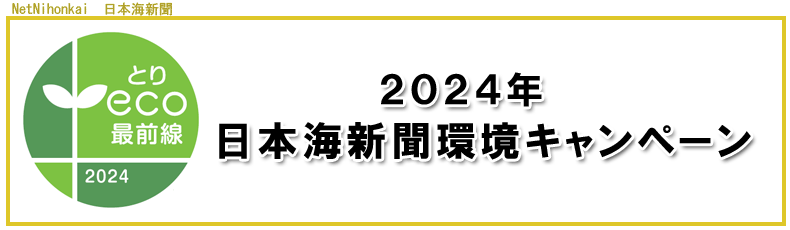| 特集一覧 |
2025 











2024 











2023 











2022 











2021 








2020 








2019 








2018 








|
|
|
vol.195 環境保全型農業の推進
2025.9.30
地球温暖化や生物多様性の危機が叫ばれる中、農業の現場からも環境課題に挑む取り組みが広がっている。化学肥料や農薬の使用を抑え、自然との調和を目指す「環境保全型農業」の推進もその一つ。土や水など地域の自然環境を守るだけでなく、消費者に安心と信頼を届ける新しい農業の形として注目されている。
地域一丸、有機農業拡大へ 八頭町「オーガニックビレッジ構想」
 |
| 収穫が間近に迫った有機米(きぬむすめ)の出来栄えを確認する鎌谷会長 |
八頭町は本年度、地域が一体となって有機農業を広げる「オーガニックビレッジ構想」を実現するための国のモデル事業に着手した。鳥取県内の自治体では、日南町に次いで2番目。今後、具体策などを盛り込んだ実施計画をまとめ、年度内にも「オーガニックビレッジ宣言」をして全国に周知したい考え。
地元にアピール
実施計画を策定する「八頭町オーガニックビレッジ推進協議会」(鎌谷一也会長)は7月24日、行政やJA、町農業公社、農家などによって発足した。8月21日には兵庫県丹波篠山市を先進地視察。10月には食イベント「八頭町マルシェ」に出店し、有機農産物を地元にアピールする。
八頭町によると、現在、町内の耕地面積約1630ヘクタールのうち、有機JAS認証面積は8・2ヘクタール(0・5%)で、実施計画には有機ほ場面積の拡大や有機農業者増を取り組みの柱に据える予定。今秋から町内小中学校5校の学校給食に有機米や有機野菜を積極的に提供していく方針もあり、必要量を逆算して有機ほ場面積の目標値も設定したい考えだ。また、たい肥のほか、液肥として利用されるメタン発酵消化液など地域資源の有効活用による循環型農業の拡大なども具体策として検討している。
就農の受け皿に
鎌谷会長(72)は「オーガニック宣言し、地域一丸で有機農業の取り組みを強化していくという方向性があれば、農産物の取引もしやすくなるし、新規就農の受け皿にもなれる。農業体験を通じ、環境への理解と共感を育めるエリアにしたい」と話す。
同施設の昨年2月からの1年間で総電力使用量は約20万キロワット時。同システムが本格起動する本年度、この外部電源分22%削減と、年間の約20トンのCO2削減を見込む。天候の条件次第では、同施設の日中使用全電源を太陽光のみでカバーすることが可能で、環境に配慮した事業を進めている。
有機農業は化学肥料や農薬の使用を制限することで、土壌・水質汚染を防いで生態系への負荷を軽減したり、土壌に炭素を貯留して二酸化炭素の排出を削減したりする効果も期待されており、環境保全型農業の一つの形態と位置付けられている。
ECOワード解説 オーガニックビレッジ
生産から消費まで一貫して地域ぐるみで有機農業の産地形成に取り組む市町村を指す。国が2021年度に策定した「みどりの食料システム戦略」に基づき、全国各地で有機農業の産地づくりを支援。8月29日現在、国のモデル事業「有機農業拠点創出・拡大加速化事業」を活用し、オーガニックビレッジに取り組む市町村は46都道府県150市町村で、30年までに200市町村を目指す。
価値や良さ広めたい とっとりエコ・グリーンフードコーディネーター 渡世唱子さんに聞く
鳥取県内外でマルシェ事業などを展開する「山陰三ッ星マーケット」代表理事で、2024年2月に鳥取県知事から「とっとりエコ・グリーンフードコーディネーター」を委嘱された渡世唱子さん(56)に活動への思いなどを聞いた。
−環境に優しい「とっとりエコ・グリーン農業」の“旗振り役”に就任した。
有機栽培をはじめ、化学肥料と化学合成農薬を50%以上減らした特別栽培の農産物など地球環境への負荷を減らし、手間をかけて高品質なコメ、野菜を生産する農家に光を当てる存在になりたいと思った。
−「とっとりエコ・グリーン農業WEBサイト」の制作を担っている。
県内の“エコ農家”を取材し、どこで誰が、何を栽培しているのか、マップに落として紹介している。農家の生の声を聞くことで、農産物の魅力だけでなく、販路開拓の難しさや後継者不足などの課題もはっきり見えており、私たちも一緒に未来の農業を考えるきっかけになっている。農家と消費者の橋渡し役として務めていきたい。
−活動の成果は。
取材先の農家に声をかけて商談が成立し、丸由百貨店地下1階の「三ッ星グランマルシェ」に仕入れるなど農家の販路拡大につながった事案もある。こだわりの農産物は健康意識の高い人からの需要も増えつつあり、少しずつ販売価格に転嫁できるようになってきた。
−有機農産物などをもっと消費者に選んでもらえるために何が必要か。
発信力だと思う。ウェブ発信に加え、農家も参加して消費者にPRする対面型のイベントの頻度を増やしていくことも大事だ。
−今後の目標は。
今は鳥取県の農産物を皆さんに薦めるのが生きがいにもなっている。地元で生産された有機・特別栽培などの農産物の価値や良さを地元の人にも伝えたい。そして、環境に優しい農産物作りに携わる若い人たちが、少しでも増える仕掛けをつくっていきたい。
わが社の環境(エコ)活動
日ノ丸産業
鳥取市富安2丁目 小山尚悟社長
創エネ推進のモデル企業
 |
| 2021年に完成した本社社屋 |
鳥取県内を中心に石油、ガス、ハウジング、観光の4部門を展開し、地域のエネルギーインフラを支える一方、創エネ分野にも力を注いでいる。
昨年開設した山陰初の複合型サービスステーションには、高耐圧ソーラーパネル96枚を設置し、自家消費型発電で年間約20トンのCO2削減を見込む。さらに電気自動車(EV)急速充電器を備え、持続可能な交通の普及を後押しする。
4年前に完成した木造4階建て社屋は県産木材を活用し、地産資源の循環利用にも貢献。「まちにやさしく、ひとにやさしく」を掲げ、地域と地球環境の両立を目指す先進的な取り組みを進め、脱炭素時代のモデル企業としての存在感を高めている。
#私たちのグリーンムーブメント−若き担い手たち
ワカメ部
板ワカメ文化継承と活性化
 |
| 世界最大の板ワカメづくりはワカメフェスの恒例行事 |
岩美町産ワカメの知名度向上を目指すとともに、海洋環境保全や資源循環、環境教育につながる活動を展開。かつて同町網代地区に50〜60軒あったワカメ生産者が1軒になった現状を受け、板ワカメ文化の継承と活性化に取り組む。
2018年に発足し、現在“ワカメンバー”として大学生30人弱を含む約50人が参加。コロナ禍の20年を除き、19年から毎春開催しているPRイベント「ワカメフェス」、ワカメを題材にした音楽や落語の創作、地元小中学校での出張授業などを通じて、楽しくワカメの魅力を伝えている。
また、同フェスで海の生きものタッチプールや海ごみ問題への啓発活動などを行い、イベント来場者の環境意識を高めている。商品として流通できない板ワカメのかけらを活用したせんべいの復活、環境配慮素材を使ったグッズ製作など、持続可能な地域資源の活用にも積極的だ。
漁師のメンバーを中心に、海の変化の発信もしていきたい考え。学生メンバーの北中健太郎さん(公立鳥取環境大4年)は「今後も地域との関係を大切に、環境や社会課題に向き合っていきたい」と話す。
|
|