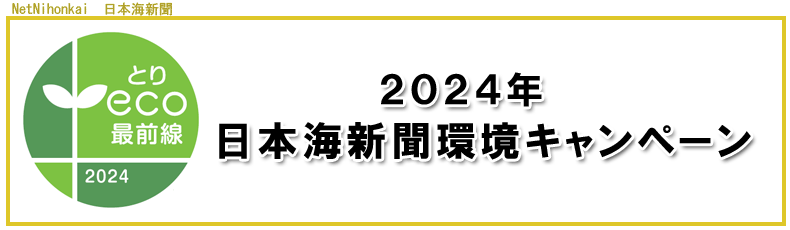地球温暖化の進行やエネルギー価格の高騰を受け、冷暖房や給湯などで多くのエネルギーを消費する住宅をはじめ、家庭の省エネ・脱炭素対策は近年ますます重要度を増す。折しも今年4月以降、「改正建築物省エネ法」の施行に伴い、住宅の新築時などに一定の省エネルギー性能を満たすことが法律で義務化された。二酸化炭素(CO2)の排出削減を目指した環境に優しい住まいづくりと暮らしを考える。
環境に優しい住まいの基本は、家庭でのエネルギー消費を減らすこと。建物の断熱性能を高め、効率的な冷暖房や給湯設備などの省エネ機器を導入することが、CO2の排出削減に直結する。近年では、太陽光発電などの再生可能エネルギーや家庭用蓄電池を組み合わせて、自宅でつくった電気をためて、効率的に使う「スマートハウス化」も広がりつつある。
既存住宅でも、複層ガラス(ペアガラス)への交換や二重窓の設置など、窓をリフォームするだけで家の断熱性能が向上。発光ダイオード(LED)照明や省エネ家電に切り替えることも、省エネ対策の一つだ。
また、地域産材を積極的に取り入れた家づくりや「木材の地産地消」の推進は、木材の輸送距離短縮によるCO2削減のほか、森林の保全・整備、林業の活性化などを促す多角的なメリットが期待される。
ゼロカーボンとっとり 大野木センター長に聞く 「診断」で無理のない削減を
日々の暮らしの中で、環境に配慮した住まいをどう実現していけばいいのか。鳥取県で気候変動対策の普及啓発を担う拠点「ゼロカーボンとっとり」の大野木昭夫センター長に聞いた。
−エコな住まいに対する県民の意識は。
以前に比べ、意識は高くなっていると思う。私自身は光熱費の高騰がその背景にあると痛感する。そういう意味でも私たちはCO2削減だけでなく、光熱費削減につながる行動変容を提案することで、家計に優しい省エネを進めている。
−省エネ生活のポイントは。
無理や我慢で省エネは続かないので、必要なエネルギーを見直し、効率よく使うことで、快適な暮らしと省エネを両立していくこと。各家庭がエネルギー消費量を把握し、その特徴を理解して、対策に取り組むことが大切だ。
−ゼロカーボンとっとりは、環境省が提供している家庭向けの温暖化対策診断サービス「うちエコ診断」を実施している。
専門の診断士が自宅のエネルギー利用を客観的に“見える化”して、無理のない形で最適な改善策を提案してくれる無料サービスで、家計の節約と環境負荷の軽減の両面で利用価値があるといえる。対面診断だけでなく手軽なウェブ診断もできるので、ぜひ活用してほしい。
−「ゼロカーボンチャレンジシート」にも独自に取り組んでいる。
CO2を減らすため、捨てる食べ物を減らしたり、水や電気を節約したりするなど、自分事として家族で挑戦できる脱炭素行動項目をチェックして応募してもらっている。2年目の昨年度は県内から966人の応募があり、CO2排出削減量は753トンに上った。イベントなどさまざまな活動を通して応募を呼びかけ、暮らしの脱炭素に向けた県民意識を高めていきたい。
ECOワード解説 改正建築物省エネ法
2025年4月施行。住宅・非住宅を問わず、同年4月以降に着工する全ての新築建築物に対して、省エネ基準への適合を義務付けた。増改築を行う既存建築物も、増改築を行う部分については省エネ基準の適合対象となる。「増改築」には修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれない。50年カーボンニュートラル達成に向け、建築物分野での二酸化炭素排出量削減を強化する取り組みの一環。
わが社の環境(エコ)活動
鳥取県生活協同組合
鳥取市河原町布袋 井上約理事長
脱炭素と循環型社会の実現
 |
| 西部支所の屋上に設置されているソーラーパネル |
豊かな地球環境を未来の子どもたちへつなげていくため、温室効果ガス(CO2)を排出しない再生可能エネルギーを活用し、脱炭素と循環型の社会の実現を目指す。
具体的には事業活動から排出されるCO2を30年度に13年度比で46%削減する目標を掲げる。これまで事業所に太陽光発電設備を設置し、約1割の電気使用量を再エネに切り替えるなどしており、現在の達成率は3割程度。
年内には地元の小売り電気事業者「鳥取みらい電力」の取次店として、CO2実質ゼロの電気を組合員家庭に供給する事業を始める。県生協総合企画室の小林茂樹さんは「地球規模の温暖化を防ぐには多くの人の理解と行動が必要。電気の地産地消を地域とともに進め、持続可能な地域づくりを支援していきたい」と話す。
株式会社建販
鳥取市叶 山内智晃社長
CO2削減へ丁寧な家づくり
 |
| 「経年美化する家づくり」をテーマに、厳選した品質の木材、天然素材を用いた住宅屋 |
厳選された品質の木材と天然素材を用いて「住まい手とともに経年美化する家」がテーマ。地域の気候・環境特性を読み解き、ライフサイクルCO2の削減へ向けて、普遍的なパッシブデザインの家を追求する。
高い躯体(くたい)性能・断熱気密性能を確保しながら、太陽光や太陽熱などの自然エネルギーを取り入れた家づくりをベースとし、年間の着工棟数を10棟までに制限し、住まい手とともに丁寧な家づくりを実践する。住まい手のプライバシー確保と将来の防犯上の観点から「完成見学会を行わない」のも信条としている。「世代を超えても愛される家・壊されない家」を目指して、創業より21年。住まい手の何げない日常の暮らしの裏方として、脈々と受け継がれる「まじめな木の家」を実践・提供していく。
#私たちのグリーンムーブメント−若き担い手たち
公立鳥取環境大「TU ES地球環境を考える会」
学びながら行動
 |
| カードゲームを通じて環境問題を楽しく解説 |
地域での環境意識向上と学生自身の環境課題への理解を深めることを目的に、活動を続けている。部員は54人。
自主勉強会や外部イベントへの参加を中心に、月2回程度活動している。昨冬に東京都であった全国規模の環境展示会「エコプロ」では、最新の環境知識などを吸収。また、植林体験やフィールドワークなど地域での実践活動に参加し、環境保全を学んできた。
学内では昨年12月、「フェアトレードを考える会」と題して「SDGsカフェ」を開催し、中学生や近隣住民にカードゲームなどを通じて環境問題を体験してもらった。さらに部員が企画・運営するワークショップで、リサイクルやエネルギー問題について学べる場を提供し、環境に対する参加者の理解と関心を高めている。
部員数の増加に伴い、組織のまとまりなどが課題に。今後、部員が積極的に参加したくなるような取り組みで、地域との関わりをさらに深める方針だ。部長の北秀虎さん(環境学部4年)は「チームとしての結束力を高め、企画力を磨き、地域に還元できる活動を続けたい」と意気込んでいる。